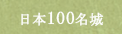宮本武蔵の続き(16)です。
家康の曾孫にあたる「小笠原忠真」は、1615年大坂の陣で父と兄を失うも、「あっぱれ!さすがは我が鬼孫じゃ」と家康から褒められる程の活躍をし、1617年信濃松本8万石から播磨明石10万石へ加増転封となり「船上城」へ入ります。そこで秀忠より西国監視役を命ぜられ、1619年忠真はそれにふさわしい「明石城」の築城を開始します。この時に武蔵を客分に招き、城下の町割りを託したようです。
武蔵は城下の南側を町人町とし、西国街道と合わせた町割りを作りました。今でも鍛冶屋町・細工町・東魚町・西魚町などの名前で残り、諸国を旅して学んだ軍略的知識も取り入れて攻めにくい構造し、かつ西国街道を中央に通し経済発展の基礎をも築いていたようです。
さらに武蔵は忠真のための憩いの場として、山里曲輪に庭園を造ります。その庭園が再現されていました。庭園の横のサービスセンターにはカフェがあり、暑かったのでお茶ならぬ抹茶アイスを食べながら庭園を眺めてみました。ちょっとだけ武蔵の気分に浸る事ができました(写真⑦)。
武蔵はここで、実兄の田原久光の子でこの時15才の「伊織」を二番目の養子に迎えます。そして忠真に仕官させてほしいと懇願し、近習として取り立ててもらったようです。その宮本伊織は忠真の下でめきめきと才能を表し、わずか5年後の20才で何と家老に抜擢されました。
明石城が完成した1624年頃、武蔵は同じく完成した名古屋城の「徳川義直」の元へ招かれます。というか明石城が一段落したこの機に、尾張へ自分を売り込みに行ったようです。そして義直の面前で、当時剣術指南役をしていた「柳生利厳」(柳生宗矩の長男)の弟子たちをあっという間に倒し、何とここで自分を利厳に代わり剣術指南役にするよう要求したそうです。この時、年俸として1億円を要求したとか(利厳はこの時3千万円)。この頃の武蔵は相当プライドも高くなり、ちょっと図に乗っていたようですね。しかし義直から断られて仕官できず、結局また明石の伊織の屋敷へ戻ります。
それから1630年頃になると、九州では各地で不穏な動きが始まります。譜代大名である小笠原忠真は九州目付の職を与えられ、播磨明石から豊前小倉15万石へ転封となり、九州の外様大名を監視せよ命ぜられました。せっかく苦労して明石城を完成させたのに、今度は九州に行けと命ぜられ、忠真はどんな気分だったのでしょうね。武蔵は伊織に同行し、再び小倉へ行く事にします。そして小倉で、またしても問題が起きてしまいます。
次は(小倉城)島原の乱に続きます。
明石駅でお腹が空いたので、明石名物で昼は「たこやき」、夜は「たこ蕎麦・たこめし」とたこづくしを堪能しました🐙。駅構内にあった店に二度も吸いよせられ、まさに「おもうつぼ」にハマってしまいました~😋!(写真⑧⑨⑩)。
+ 続きを読む