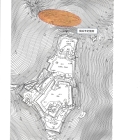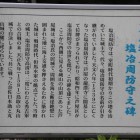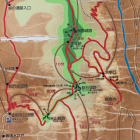鞆からの転戦で本日の締めは福山城 改装完了になり訪問しました。当日福山市内あちこちでアニメイベントが開催中でお城もたくさんのコスプレイヤーだあふれていました。さて、鞆城の投稿で予告しました鞆の浦保命酒の数あるお店の中の岡本亀太郎本店、この店舗は明治初期に福山城の長屋門の一つが移築されたものだそうです。建築様式からみて福山城の江戸初期の建築物でたいへん貴重な遺構らしいです。皆さん是非お立ち寄りを!泊まりの駅前ホテルの部屋からはライトアップされたお城を満喫。晩御飯は恒例の孤独のグルメで地元の魚を堪能しました。
+ 続きを読む