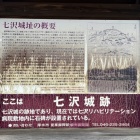【とことん名護屋城-②】徳川家康と前田利家
(2025/11/23 訪問)
ここからは先生方の講演の中から、興味のある内容をピックアップし、その場所を訪れて行きます。まずは「平山優」先生の講演の中に出た、徳川家康と前田利家の対立からです。
天守の北東部、山里丸から600m程の離れた場所に、「徳川家康陣跡」があります。最初その隣には、前田利家が陣を張る予定だったそうです。しかしいざ造ろうとすると水がない! それで井戸の取り合いになったとか? 名護屋の地は良好の港に恵まれていますが、最大の欠点は水が無い事です。確かにこれだけ海に近ければ掘っても海水が多く、真水が出る場所は貴重ですよね。
よってその時は伊達政宗が仲介し、利家の方が名護屋城の南東部(現在の道の駅桃山天下市の場所)に移りました。この頃から徳川家康と前田利家は対立するようになったのかもしれません。
まずその移った「前田利家陣跡」へ行きました。ここでは発掘調査が最近行われ、そこでわかった事ですが、ここは13ヘクタールの規模で豊臣秀保に次ぐ2番目の大きさの陣だったそうです。そして8千人の兵を収容していたとか。入口には石垣をともなった桝形門と大きな水堀に囲まれ(現在の道路)、その外と内は土橋でつながれ、さらに玉砂利や庭園もあった事も分かったそうです。これはもう陣というより立派な城ですね。大変多くの方が説明会に参加されていました。
次は「徳川家康陣跡」に行き、そこに立ってみました。今では防風の木々でふさがれていますが、当時はここから海がよく見えたと思います。そして後ろを振り返ると「ハッ!」としました。ここからは名護屋城の天守が、見上げるように実によく見える場所である事がわかりました。逆に言えば、秀吉からも家康の行動を逐一監視でき、睨みをきかせる事ができる場所だったという事です。きっと家康はその屈辱から、「いつかは豊臣秀吉と前田利家を倒し、絶対に自分が天下を取ってやる!」と、毎日ここから天守を見上げ、密かに野望を抱いていたのかもしれませんね! 徳川家康の陣から見上げた様子を、唐津城の天守を合成して作ってみました。こんな感じに家康の目には、写っていたのではないでしょうか?(合成写真⑤)。
次は(秀吉と茶々)の話に続きます。
+ 続きを読む