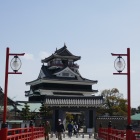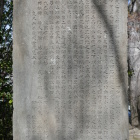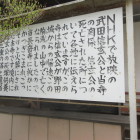一ノ岳山頂付近が城跡との事で訪れました。
南畑ダムの周辺に登山口があります。
今は入り口にロープがはられている為に入り口に車を停めて登りました。
舗装された道をしばらく歩くと山へ入る道がありそこからはある程度の登山になります。
けっこう急な登りを登って行くと山頂付近は木に結ばれた赤い目印を頼りに山頂に到着です。
山頂付近には竪堀、石積みらしき遺構は確認できました。
しかし、目当ての石垣を見る事ができませんでした。
様々なサイトなどを確認して翌々日にリベンジしましたが、また見つける事ができませんでした。涙
入り口は合っているようです。
登山口からの道も正解のようですが、山林に入ってからの分かれ道を左に行くと石垣があるとの情報があるのですがどうしても左にそれる道がわかりません。
いつの間にか頂上に着いてしまいます。
大雨の影響なのか、木が倒れていたり道が削れている所も多く見られます。
もしかしたら以前はあった分かれ道が崩れてしまったのか。
どなたか御存知の方がいたら教えていただきたいです。
+ 続きを読む