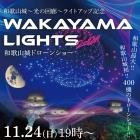平戸城の築城は古くは松浦鎮信による日之嶽に築いた城とされます。慶長18年(1613)に火災に会い、長らく平戸藩は「城なし」の状態でしたが元禄15年(1702)に再築城を願い出て翌年に許可が下りました。
二の丸の乾櫓が天守代用とされ、今は模擬天守が建っています。また狸櫓と北虎口門(搦手)は現存の建造物として残っています。
四代藩主・松浦重信は「武家時記」の作者である山鹿素行と親交が有り、平戸に招こうとしますが果たせず、後に一族の山鹿高基・義昌を藩士として迎え入れます。平戸城築城指導は義昌によって行われ、山鹿流軍学に基づく縄張りが成されているとのことです(wiki参照)。
話は変わりますが、白峰教授が論文の中で「武家事記」記載の関ヶ原の合戦図と、参謀本部の作成した「日本戦史関ヶ原役」を比較しています。非常に細かい部分まで丁寧に説明してくれているので、明治に神谷道一氏が書かれた「関原合戦図志」が「武家事記」を参考にしていることが良くわかります。
神谷氏は「武家時記」記載中の矛盾点も修正し、自らの視点を南宮山の布陣に反映させるなど非常に真摯に歴史に向かい合っています。
残念ながら、「武家事記」の内容そのものの信憑性が乏しいので、「関原合戦図志」の布陣図も正解とは思えないのですが、参謀本部に都合よく改修された現在の関ヶ原の布陣よりは、よほど好感が持てます。
+ 続きを読む