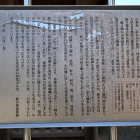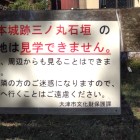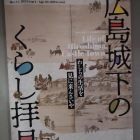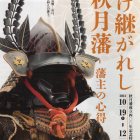【城域4:曲輪群[4-3]】
<登城路>麓に最も近い曲輪群で、登城口は聖護院宮墓地の正面右手の崖をよじ登れば曲輪群の南端に入れます。聖護院宮墓地へは<35.032576, 135.797845>から北へ狭い道が伸びています。全ての曲輪群を巡る方がいらっしゃれば、ここから攻めるのがベターかと思います。
<見所>堀切・竪堀・曲輪群
<感想>北東方向に伸びる尾根上を削平した10程ある連郭の曲輪群でこの区画だけで1つの城塞くらいの規模があります。曲輪群には堀切が4か所あり南端・中心・北端、中心の大堀切の北側が主要部の曲輪と思われその曲輪の北側の4か所です。堀切土橋の遺構が良く残っています。曲輪群は南から東側に長升形の虎口、曲輪の真ん中に竪土塁の堡塁があり、西側から上がってくるスロープ状の虎口を防御しています。中心の大堀切の南側に東斜面に落ちる大竪堀が見応えあります。中心の大堀切の北側が主要部であった感じで、段々がくっきりしています。「京都府中世城館跡調査報告書」の縄張り図の8番の倒木が多い曲輪が主郭であろうかと思いました。北端は大きい堀切土橋になっていて、土橋から東に曲がって尾根を登り切りると曲輪群[4-2]に繋がります。曲輪群[4-2]は単独でここだけ特異な雰囲気をもつ曲輪群ではあるがこの曲輪群[4-3]とほぼ繋がっているため互いに連携していたと思われます。この曲輪群[4-3]は将軍山城の導入部を守る最前線の曲輪群という印象を受けました。なかなかの見応えです。次は曲輪群[4-2]の投稿です。
+ 続きを読む