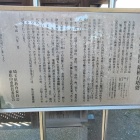城びと先人二人のレポートを見て、行きたい城にノミネート。お二人に倣って、県道23号沿いの南側から登城。道端に登城口の看板がありました。県道23号線は旧国道とのことですが、普通車だとちょっと躊躇するような道幅。登城口の看板がある谷筋を少し登ると、左手にトラロープが張ってあり、尾根筋に取りつきます。
本郭の説明板では、登っていくこの尾根は城域として示されていないのですが、道々に、空堀やうね堀の表示板が立っています。畝堀は、比較的平らな尾根筋に平行に2本並んでおり、畝堀なんですかね。ぴーかるさん指摘のように、自然地形のような。とは言え、説明板の城域にもたくさんの表示がされており、よく管理・維持されていると思います。「槍突場」の表示を始めて見ました。阿波の三好氏が由良港に上陸して、その背後の小坊子城を拠点にしたとのこと。木々の間から、由良港が見下ろせました。
+ 続きを読む