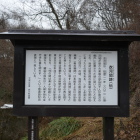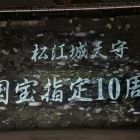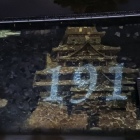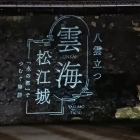新青森駅前の東横インに前泊。
釧路まで8時間の列車旅に耐えられるか少し心配でしたが、車窓を流れる美しい景色と脳内リフレインする「北の国から」のメロディに浸りながら快適に過ごしました。
釧路駅から路線バスで釧路市立博物館へ。
受付で史跡釧路川流域チャシ跡群のリーフレットをいただきました。
ハルトルチャランケチャシは博物館の近くです。
右手に春採湖を見ながら歩いていると少し出っぱった緑の森が見えてきました。
ここだ!
ドキドキしながら道路側からアプローチ。
大きく弧を描く2条の壕がここが特別な場所であることを教えてくれます。湖畔に佇むと切り立った崖の上であることも認識でき、外界との違いを肌で感じることができました。
人生初・チャシとの対面は「お城」の世界観をぐっと広げてくれました。
+ 続きを読む