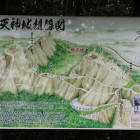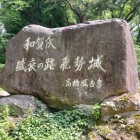滋賀県長浜市の妙法寺には羽柴(豊臣)秀勝の墓があります。豊臣秀勝というと、豊臣秀次の弟で三好(木下)吉房の子である秀勝の方が有名ですが、こちらは秀吉の長浜時代に生まれた子・石松丸で、側室の産んだとされています。
秀勝と名のつく人物は他にも、織田信長の四男で秀吉の養子となった秀勝(於次)がいます。秀勝多いです。
この後、秀吉に長らく子が生まれなったことを考えると、本当に秀吉の血を引いているのか不明ですが、戦国の武将である秀吉が子供を欲しがっていたのも事実だと思います。
太郎坊阿賀神社は古くから神の宿る霊山として崇拝され、聖徳太子・伝教大師最澄・源義経らの崇敬を受けています。境内には「夫婦岩(めおといわ)」と呼ばれる巨岩があり、高さ20m近い巨岩の間に1mに満たない隙間が通っています。なんとなく豊橋市の石巻山に似ている気がしますが、ここに城跡があったという伝承はありません。
+ 続きを読む