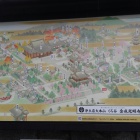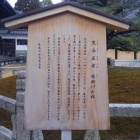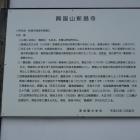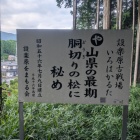金戒光明寺は京都市左京区にある浄土宗の大本山です。承安5年(1175)頃法然が当地に草庵を建てたことが由来とされ「くろ谷さん」の愛称で呼ばれているようです。境内の阿弥陀堂は慶長10年(1605)に豊臣秀頼によって再建されたもので、熊谷直実の鎧懸の松の他、徳川二代将軍秀忠夫人の崇源院(江さん)の墓も有ります。
寺院としては堅固な造りで江戸初期に黒谷と知恩院は徳川家によって城構に改められています。幕末に松平容保が京都守護職に就任すると会津藩の本陣が置かれ、当地で浪士組の芹沢鴨・近藤勇らが容保と謁見を果たしました。その後、8月18日の政変の日に「新選組」の隊名を拝領し市中取締の命を受けています。金戒光明寺も新選組とゆかりの深い場所で、「新選組発祥の地」とも呼ばれています。
明日から合戦です。ヨシ姫も良いのですが、個人的には戦闘員のお姉さんも登用したい。運に左右される要素も大きいですが。
+ 続きを読む