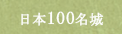代表して今帰仁城のレポートとして書いていますが
日帰りで沖縄の五城を制覇した時のお話です
沖縄の観光タクシーはわりとお安いので
大変助かりました
私の場合は那覇空港から
スタンプラリー状態で6時間で回りましたが
(高速料金は別にお支払いしましたが2000円くらいだったかと思います)
現在は、北部の設定となるので7時間〜の料金になるようですね
もう少しくらいはゆっくり見たい方でも
空港から空港連絡バス(やんばる急行バス)で今帰仁城址迄行かれて見学し
そこで待ち合わせをして空港まで戻りながら残り4城を回る事は出来ますし
終着地点を首里城にすれば、さらにゆっくり見学出来ます
首里城から空港迄は、ゆいレールというモノレールが便利です
沖縄観光タクシーの貸し切りプランは
予約&打ち合わせが必要ですので、お電話して相談されてみてください
ご参考になる方がいらっしゃいましたら幸いです
(^∇^)ノ♪
+ 続きを読む