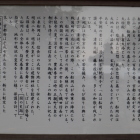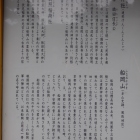枕草子に「岡は船岡。片岡。鞆岡は、笹の生ひたるが、をかしきなり。談の岡。人見の岡。」とあるそうな・・「生ひたる」は成長したを示すそうです。笹好きですか?
いとも雅な感じがしますが、舟岡山の伝承はいずれも血生臭いです。応仁の乱の頃から、陣所として使われたり、それ以前にも火葬場となったり処刑場だったりしたそうです。この山から見える景色が最後の光景になるわけね・・五山の送り火が良く見えるらしい。
舟岡山には織田信長を祭る「建勲神社」があります。織田信長は愛知県が誇る三英傑の中では、唯一本当の意味で「天下」を取っていない人物です。正直、畿内を制しただけで「天下」って、全然ピンと来ないんですよ。
そもそも本人が一番納得していないと思いますね・・光秀~~💢💢💢
イオさんの投稿にある横堀を見に行きたいですね。捲土重来・・したいなあ。
+ 続きを読む