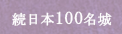前回登城時は時間が無くリベンジを誓っていました。
今回再訪、目的は登り石垣です。
寒いけど晴れた冬の空に模擬天守も映えていました。
馬屋跡の駐車場に車を置き、まずは本丸に向かいます。
大石段も石垣も素敵、さらに本丸からの絶景を楽しんだ後西の丸へと向かいました。
籾蔵から200m進むと曲輪が見えてきます。
もちろん脇にそれて石垣を見ながら半周、西の丸は出城のような役割で建物は無かったとされています。
また、残念石もありました。
引き返し西側の登り石垣を目指します。
搦手の石垣は工事中ですが休工中、降りれそうだったので進んでみました。
暫く降りると右手に登り石垣が見えます。
なかなかの規模、見応えありですね😀
八王子神社に向けての登城路を登り再度山頂部へ。
今度は東に進みます。
二段の郭の下から東の登り石垣を望みます。
さすがここは遠景のみ、それでも迫力がありました🥹
目的は達成、武者溜から東一の門まで行って撤収しました。
絶景と登り石垣だけでなく見どころは多い城ですね。
【見どころ】
・絶景
・登り石垣(東西)
・各所の石垣
・本丸への大石段
+ 続きを読む