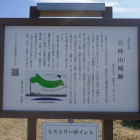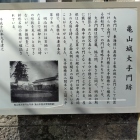熊のお話(熊は関門海峡を渡れるのか?)
(2025/11/05 訪問)
熊本に所用で来て早く終わったので、ならばと熊本城をぐるりと一周してきました。
宇土櫓を見ると、櫓の土台石垣の解体工事が終わったところでした(写真①②)。また小天守の下では、石垣の積直し工事がいよいよ始まっていました。クレーンで100~200kgもある石を一つずつゆっくりと下ろし、きっちりとパズルのようにはめ込んでいく様子を見ていると、方向や位置を寸分も間違わずに載せないといけないので、こちらにも緊張感が伝わってきます(写真⑤)。
ではここからは、しんちゃんの好きな熊のお話です。 テレビを見ると毎日のように熊の話題が多いですが、九州には熊がいない事は以前お話したと思います。
熊本はその名の通り地名に「熊」が付き、特にキャラクターが「くまモン」なので、いかにも熊が多い県のように思われがちですが、元々は「隈本」という地名で、加藤清正が隈の字に「畏れる(おそれる)」という意味があるのを嫌って、「熊本」と改名したそうです。20~30年くらい前に祖母・傾山系(大分県と宮崎県の県境)でツキノワクマが目撃されたのが最後で、それ以降現在まで、九州での熊の目撃情報はありません。よって現在九州には熊はいないと宣言されています。その時の熊も野生ではなく、だれかが本州から持ち込んだものだったそうで、自然と絶滅したようです。
本州での南限の生息地は、3年位前までは島根県でしたが、去年から山口県の岩国などで熊が目撃されているので、このあたりが現在の本州で最も南に生息している熊と思われます。
ではいつかは九州にも熊が現れるのではないか? 福岡の某テレビ局で特集がなされていました。専門家の推測によると、熊は泳げますが関門海峡は流れが速すぎて船も多いので、それで現在まで泳いで渡れなかったのではないか?と推測しているようです(なるほど🤔)。しかし油断は禁物と、関門海峡では本当に泳いで渡る熊がいないか、今では常時監視しているそうです。
熊本城をぐるりと一周した後は、城東側にある通町筋で熊本ラーメンを食べました(写真⑨)。そして店を出ると、目の前を何とくまモンが歩いていたのでビックリです(写真⑩)。これからすぐそばにある「くまモンスクエア」に出勤するようです(県庁の公務員なので忙しそう)。手を出すとハイタッチしてくれました。この熊本が日本で唯一、熊と人間が平和に共存できている場所なのかもしれませんね!(🤔???)。
+ 続きを読む