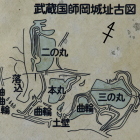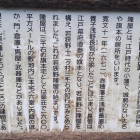古都奈良の中心部に見事な二重空堀がある城跡
(2023/06/17 訪問)
【西方院山城】
<駐車場他>タイムズ東大寺転害門西24時間550円に駐車しそこから徒歩
<交通手段>車
<見所>竪堀・2重空堀
<感想>日帰り奈良ちょこ城150㎞の旅2城目。西方院山城は1444年に古市氏が筒井氏に対抗するため鬼薗山城の代わりの城として築城を開始しましたが、一旦中断して鬼薗山城を完成させたために途中で放置されました。1478年に古市氏が西方院山城の築城を再開して完成させますが、城が完成して3日後に筒井勢に攻められた際に城兵が火を放ち焼失落城しました。
2019年にすぐ隣にある奈良ホテルになっている鬼薗山城跡に行きこの西方院山城もチャレンジしようとしましたが、人の往来が激しくて市街地の中、山に入り込むを躊躇して断念しました。今回は先達方の投稿を参考に<34.679190, 135.835093>の土塁端からよじ登って登城しました。上記ポイントから登っていくと、主郭背後の土塁と池方向に落ちる竪堀があります。主郭は瑜伽神社とその裏にある広い削平地になります。主郭西側に大きい2重空堀が残り見応えがあります。空堀の最南上部に虎口跡があり数個石列が残ります。奈良公園のすぐ南、市街地の真ん中に土の遺構のある丘城跡があるのは珍しい。
<満足度>◆◆◇
+ 続きを読む