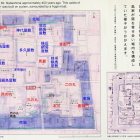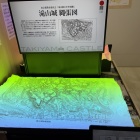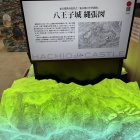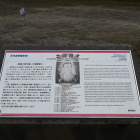小天守めぐり、まずは東小天守からです。案内板によると東小天守は高さ9mの石垣の上に建つ三重櫓とのこと。
でも外観は二重の多聞櫓で北向きに妻の千鳥破風が有り、三重目は多聞櫓の二重屋根の上に載せられた望楼です。多聞櫓が大きいので三重櫓が小さく見えるわけですか。さすが天下の姫路城ですわ。
小天守一つとっても吉田城の鉄櫓と同じくらいか、もっと大きい。でも吉田城の方が姫路城よりも「お兄さん」ですぞ。池田輝政繋がりで本丸の構造も少し似ています。
東小天守を見た後はロの渡櫓を通って乾小天守に向かいますが、この渡櫓がまた凄い。凄い窓の数です。普段見れない光景が広がっていて目にするものすべてが新鮮です。姫路城・・改めて凄い城ですね。2000円ぐらいに抑えてもらえると、だいぶ行きやすくなるんだけどね。
一見さんの外国人さんと同じ値段は「城ずき」としてはちょっとキツイよね。そういうこと言うと、嫌なら来るなって言われるんだろうけどね~
+ 続きを読む