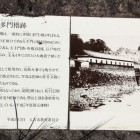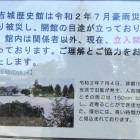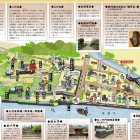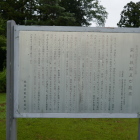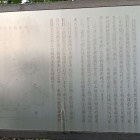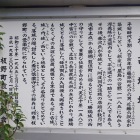「道の駅ばんだい」は福島県耶麻郡磐梯町にある道の駅です。愛称は「徳一の里 きらり」ですが、お土産コーナーの一角にバンダイのプラモデルを販売しているコーナーがあり「ばんだい」の名称のほうが先行して有名になっている感があります。
店舗入り口に飾ってあるガンダムの立像は、だいたい「へたれガンダム」と同じくらいの大きさです。うん、こうして見ると「へたれガンダム」とは違った良さが有りますね。へたれてないガンダムも悪くないです。
特筆すべきはバンダイのプラモ売り場の上段に、ちゃっかり古川プラスチック製の「べこプラ」が売っていることです。基本的なパーツは2つ(!)。一応「赤べこ」の名称の書かれたパーツは付属しますが、本体を形成するパーツは2つです。
価格は税込み1450円‥私、プラモ暦長いですが、正直な感想を申し上げると「高くねぇか?」 しかもパーツが2つ?
首とか可動しないんだ‥。正直買うべきかどうか悩んだので、店の人に聞いてみたところ、昨日発売されたばかりで30個以上売れているとのこと。売れてるんだ、コレ‥あきらめて買うことにしました。これをどうやって仕上げるか、完成はしばらく先になりそうです。
※道の駅ばんだいに「へたれガンダム」は入っていません。
+ 続きを読む