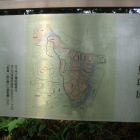感状山城は鎌倉時代に瓜生左衛門尉によって築かれたとされています。南北朝の時代には播磨国守護・赤松氏一門の居城となり、赤松円心は足利尊氏の側につきました。尊氏が九州へ落ちのびた後、建武3年(1336)に新田義貞の大軍が播磨に侵攻してきます。
円心は白旗城に籠り、感状山城には円心の三男の赤松則祐が籠りました。則祐は義貞の家臣・徳力秀隆を退けることに成功し、尊氏から感状を賜ったことから感状山城の名が付いたとされています。
「羅漢の里」の近くに専用の駐車場があり、登城道も付いています。途中に「へたれガンダム」系の木造のオブジェが数体あり、訪問者を出迎えてくれます。しばらく登って行くと物見岩と言われる、岩がごろごろ転がっている見張台らしき郭があり、三郭らしき場所から東へ登って行くと主郭のある尾根にたどり着きます。主郭から二郭周辺の郭は周囲を石垣で固めてあり、見ごたえがあります。
+ 続きを読む