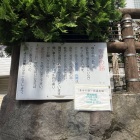駒ヶ嶺城は永禄年間(1558~1569)に相馬盛胤が伊達氏に対抗するため、新地の繋ぎとして築きました。城代として藤崎摂津が置かれ、天正17年(1589)子の治部の代に伊達政宗に攻められ落城し、伊達政宗は城代として亘理美濃、黒木中務などを置きました。
慶応4年(1859)戊辰戦争の時に、仙台伊達藩はここに本営を置き、新政府軍と戦いましたが、8月11日に落城しました。
城址には北側から迂回して入って行き本館を目指します。江戸時代には要害の名を外されていますが、構造はしっかりしていて遺構も残っています。北側から三ノ館・本館・西館が連なり、本館の東側下段に二ノ館が控えています。
本館北側から西・南にかけ空堀が残っていて、南北に虎口が付いています。南の(喰違い)虎口の先に土橋がかかり、西館から腰曲輪を経て下山しましたが、そこにも空堀があったようです。
+ 続きを読む