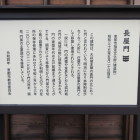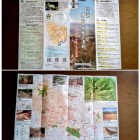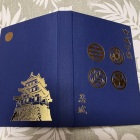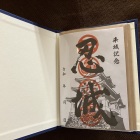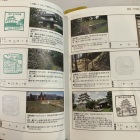【鳥羽山城】
<駐車場他>鳥羽山公園駐車場数十台分あり。
<交通手段>二俣城に駐車し徒歩
<見所>主郭虎口跡・主郭を取り巻く石垣・石段
<感想>日帰り今シーズン山城ラスト旅2城目。第41・42回日本100名城、続日本100名城に負けない名城で特集された鳥羽山城に行ってきました。二俣城を先に行き、両城は一城別郭ともいわれているので、その繋がりを確認するため二俣城の南端から徒歩で行きましたが、城の間は現代の河川敷の土塁となっていました。城跡は山の中腹まで道路が通っていて、城跡の山頂公園にいたる遊歩道は数カ所ありますが、道路脇から石垣が残された曲輪の遺構があちこちに見られます。城郭の構造は山頂の主郭を広く削平して山の形状に沿って放射状に帯曲輪や広い腰曲輪を設けています。広い主郭内部は見応えがあり、周囲は石垣で取り巻いています。主郭内部には石垣の虎口跡・推定の庭園跡・石組暗渠の遺構が残されています。石垣は角のある石と丸い天竜川の河原石の2種類を使用しています。丸石は石垣の間詰めにも利用されていて、主郭を取り巻く石垣は長く遺構が残され見応えがありました。特集記事で後世に改変された部分も多いとあったので、見定めて散策すると良いかもしれません。
<満足度>◆◆◆
+ 続きを読む