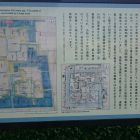詳細は不明ながら、室町期に越賀氏によって築かれた城で、九鬼嘉隆の侵攻に対して、越賀隆俊は越賀城に籠城して抵抗した後、和睦して九鬼水軍の一員となり、隆政、隆春と三代にわたって九鬼氏に仕えました。
太平洋に突き出た小さな岬に位置し、三方を海に囲まれた単郭方形の城で、北側の集落との間を堀切で断ち切っています。堀切の西端に主郭に至る登城路が設けられていますが、時季的に藪に沈んでいて突入するのはためらわれます。それでも勇を鼓して、藪をかき分け蜘蛛の巣を払いながら進んで行くと…主郭もやっぱり藪の中でした。下調べでは中心部は畑とのことでしたが、もう何年も放置されているようで、笹藪が激しく茂っていてとても入り込めません。かろうじて北東隅の土塁に石組みの穴(井戸? 古墳跡?)が見られたくらいでした。
なお、越賀城から西に車で約3分の普門寺は、隆春が隆政のために建立したとされる越賀氏の菩提寺で、境内には越賀氏三代の墓所があります。普門寺の寺紋は越賀氏の家紋と同じ桧扇(七本骨扇)のようですが、門の脇には桧扇紋の瓦が並べられていました。
+ 続きを読む