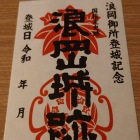横須賀城の主郭部は本丸に天守台を設け西に西の丸、本丸南に南下曲輪、その下に南下枡形の構造でした、横須賀城古絵図を見ると、天守台には四層四階の層塔型天守が聳え四方海上を睨んでいた様です(御天守想像図は本丸南下虎口の案内板掲示板の写真付き散策マップ?の下に載っています)、また南下枡形門の北側玉石垣上には二層の櫓門が枡形横幅いっぱいに設けられていた(古絵図によると)。
横須賀城の特徴である、玉石積み石垣は本丸南下側の正面と左右面、一段下がった南下枡形門の正面と左右面、本丸に南東面の正面と東虎口に積まれている、玉石の曲面、石積郭の曲面が穏やかでかわいい、城主も余程石垣に拘ったのでしょう、玉石は近くの天竜川、大井川、太田川から産出された事でしょう、説明文では天竜川と記されていました。
北側、東側の裏手は土塁で高切岸に成っています、北の丸側から眺めると高い切岸は圧巻です、時期的に染井吉野桜は終わって居ましたが、チラホラ名残の桜が目を楽しませ、新緑若葉が目に眩しく光ってる良い城探訪でした。
+ 続きを読む