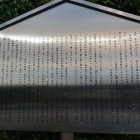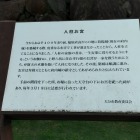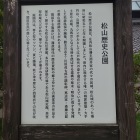「特別版 お城EXPO in 姫路」3日目に行きました。もともとは一人で行くつもりでしたが、堀めぐりは7月にしてしまったし、どうしようかと考えていると、子どもが「松丸くんの謎解きイベントをやってみたい」「くまモンにも会いたい」というので、家族で行くことに。
姫路に着いてまずは謎解きイベントに挑戦し、昼食(まねきのえきそば)を摂ってからアクリエひめじへ。アクリエひめじに至るスロープ脇の植込みには姫路城外堀の石垣石が展示されていました。説明板によれば敷地内には他にも7箇所に石垣石が設置されているそうで、全部探してみたいのは山々なれど、家族に呆れられるので我慢我慢…。すぐ近くまで来ていたんだから、先日の外堀めぐりの時に存在を知っていればなぁ…。
入城すると、当日パンフレットと一緒に受け取った謎解きイベントのお城EXPO限定ミッションに挑戦しつつ、まずは親子向けとされる「姫路城の基礎知識&お城クイズ」に参加しました。城びとの連載やテレビなどでいつも拝見してはいるものの、実際に加藤理文先生にお目にかかるのは初めてだ…と感慨深い私に対し、子どもの注目はマスコット役で登場したしろまるひめ。「モチ」とも呼ばれるひこにゃんに劣らぬもちもちっぷりに加えて、意外に横幅があるため狭い通路を歩くときはカニ歩きになるなど愛嬌たっぷりでした。本題のお城クイズ(三択)は全問正解(うち1問は自信なし)できましたが、三国堀には池田輝政が改修した際の石垣の継ぎ目があるとの解説には、何度も目にしていながら見えていなかったことを痛感。それなりにわかっているつもりでも、こうして講義を受けると新たに知ることはいくらでもあるものですね。帰宅して過去に撮った写真を見直してみても、しっかり石垣の継ぎ目が確認できました。
続いては、くまモンのイベントステージへ。くまモンも写真や映像では何度も目にしてはいるものの、実際に見るのは初めてでしたが、一口にゆるキャラと言っても、ひこにゃんやしろまるひめはゆったりした動きであるのに対して、くまモンはステージ上を所狭しと駆け回り、飛び跳ねるわ、横になるわ、客席に降りて行くわとアクティブ&パワフルで、なるほどこれは人気があるのもわかるな、と頷かされました。お城EXPOのステージということで、くまモンは陣羽織を身にまとい、熊本城クイズなども出題され、ステージ後には子どもが「熊本城に行きたい」と言い出すほどでした(私も行きたい)。さすがは熊本県の営業部長、いい仕事をしてるな~。
くまモンの後は、子どもと家内が広島城のワークショップ「しろうニャハットを作ろう!」に行っている間に、城めぐり観光情報ゾーンへ。まずニッポン城めぐりでガラポンを回し(姫路城だけに千姫…はすでに居るので、越前北ノ庄城天守を)、その隣の城びとブースに行きました。お目当ては(朝田さんと同じく)「お城かるた」の進捗確認。サンプルくらいは出来ているのかしらん、と思いきや、当初想定していた箱のサイズに収まらないため見直し中とのことでした。100名城だと読み札+絵札で200枚必要ですし、百人一首サイズになりますもんね。
そして、城めぐり観光情報ゾーンや「姫路城世界遺産登録30周年記念展示」をひとめぐりしたところでワークショップを終えた子どもと合流し、お城模型展や大甲冑展を見学して(姫路城下町スクールサミットを忘れてた…)、お城EXPOはここまで。その後は謎解きイベントの続きで姫路城下町を歩き回り、姫路駅の播州うまいもん処で夕食(姫路おでんと姫路玉子焼き)を摂って姫路を後にしました。一人で来た時のように好き勝手に見てまわれない不自由はあるものの、ゆるキャラにクイズにワークショップと子どもにも楽しめる企画がたくさんあって、お城EXPOは家族で来ても楽しいですね。
…最後にお詫びと訂正?を。先日の外堀跡発掘調査現地説明会の投稿で「発掘調査の成果は「特別版 お城EXPO in 姫路」の「姫路城世界遺産登録30周年記念展示」でも紹介される」と書きましたが、見当たりませんでした。どこで聞いた(見た)話だったか今となっては確認できませんが、お城EXPOと同日から来年3月末まで開催されている姫路市埋蔵文化財センター主催の「姫路城世界遺産登録30周年記念展 姫路城」で紹介されているのかもしれません(未確認ですが)。発掘調査現地説明会も埋蔵文化財センターの企画でしたしね。いずれにせよ誤った情報を流してしまい申し訳ございませんでした。
+ 続きを読む