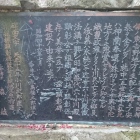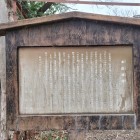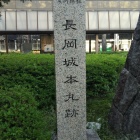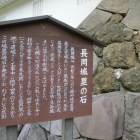室町幕府管領細川政元の家臣で山城国守護代香西元長の城と伝わっています。嵐山の標識がある主郭から尾根に曲輪が展開しています。藪になっている所もありますが、曲輪の雰囲気はわかりました。南東の虎口で石積みが確認できます。下山後、資料で確認すると竪堀があったようですが、見ていません。遺構はあまりないという先入観があり、予習を怠りました。(いつものことですが)
阪急嵐山線嵐山駅より京都一周トレイルコース入口(西山26)まで徒歩3分、そこから嵐山城への分岐点(西山33)まで約25分、さらに城址まで約25分かかりました。道は概ね整備されていますが、途中に低い岩場が1ヵ所ありました。途中の尾根から渡月橋等を見ることができます。
+ 続きを読む