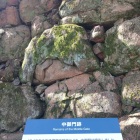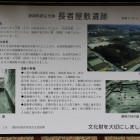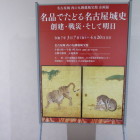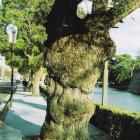秋田県の城びと未投稿城,これで解消です。先週から廻ってきた6城の近くに,アップデートしたくなった2城がありました。白根館,楢岡城。合わせて攻城してきましたので,随時レポートします。
白岩城ですが,やはり先週スルーして正解でした。5~7日ほど経過したと思われるクマのフンがありました。井戸の台を廻る新作農道ルート(左廻りルート)です。クマは移動距離が長いですが,ホヤホヤの産みたてフンがあったら要注意です。クマの放フンのほとんどは「フン止め」という目的で,「ここから先は立ち入るな」というマーキングです。子育て中はとくに危ないケース。万が一進入した場合,通常なら唸ったり地面を強打したりして威嚇するのですが,昨年あたりから人身被害が多い秋田県では「威嚇ナシ」で襲ってきます。東北地方以外でこんな情報が流れてくるのは,栃木県,群馬県,長野県,新潟県,北海道ぐらいまでだと思います。
という事情を知り得ることから,秋田県を私が引き受けました。
そんな覚悟をして攻城したごほうびか,主郭最奥の曲輪から延びる竪堀を見つけることができました。画像ではわかりづらいと思いますが…。GWには草木に埋もれてしまうと思います。
ようやく達成感に浸っているので,秋田県コンプリートは考える余地も覚悟もまだまだです。考えるのであれば,カンジキを購入することになるでしょう…。
+ 続きを読む