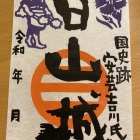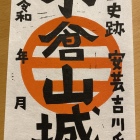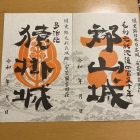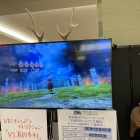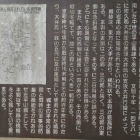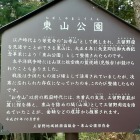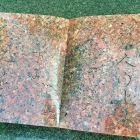豊岡市役所出石総合支所駐車場(出石城三の丸跡)から有子山を見ると、
山頂の本丸跡の石垣、および吹き流しが見えました。
出石城稲荷曲輪の東隅に登山口があります。
本丸まで980mですが・・・。
前半は登りの連続です。
竹を階段状に配置してあるのですが、
ガレ石も多いです。
勾配が急なところにはロープが渡してあります。
片手でロープを握り、もう片方の手で杖(登山口に置いてあります)をついて登りました。
登山口より33分、中間地点へやってきました。
ここまでは厳しい勾配でしたが、以降はなだらかな山道です。
心肺はずいぶん楽になりましたが、足はかなり疲れがたまり、引きずるような感じで登り続けました。
主郭へは、登山口から1時間かかりました。
山頂に主郭が置かれ、階段状に曲輪がつくられています。
帰路は、登りと同じ経路で降りてきました。
中間地点以降の部分にさしかかりましたが、下りですので心肺はさほどキツくありません。しかし、急勾配であることに加え、浮き石があること、それが落ち葉に隠れて見えないことで、ズルッ、ズルッと滑りまくりです。
その都度、ロープと杖を使って踏ん張るのですが、足がパンパンになってしまいました。スキー初心者が始めてゲレンデに出た時みたいです。
所要時間は、1時間50分でした。
+ 続きを読む