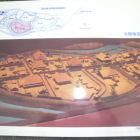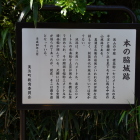お正月に会津若松城(別名鶴ヶ城)に行ってきました。
この城は1384年に建てられた城で蘆名氏、蒲生氏、伊達氏、上杉氏などの東北の豪族が入城していて、城下町も栄えていました。1869年、松平容保が率いる旧幕府軍が立てこもる会津若松城は新政府軍との激戦の舞台になりました。一日に二千五百発もの弾丸を浴びたともいわれていますが、耐え抜きました。降伏はしましたが、落城はしませんでした。
期待以上の天守、石垣の迫力に圧倒され、さらに雪が降る冬にいくとより鮮やかで幻想的です。もちろん青空との相性も抜群です。四季折々の景色を楽しめるので皆さん是非行ってみてください。
あと名物のソースカツ丼もお忘れなく!
+ 続きを読む