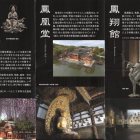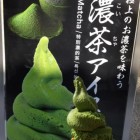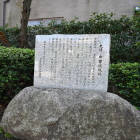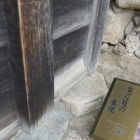(続き)
八番門跡から天守曲輪を出ると、本丸東辺に長大な石垣が見えます。宮川の断崖になっている東辺への備えとして築かれた南北80mにも及ぶ石垣で、石垣上の月見櫓や矢切櫓、太鼓櫓へと続く合坂も設けられています(立入禁止ですが)。石垣南端の石段は上れるようなので行ってみると、太鼓櫓跡の下を通って包櫓跡に行くことができました。いったん表鉄門跡を出て、包櫓跡に東接する十四番門跡から東辺石垣の外側へ。左手には太鼓櫓の石垣が聳え、右手の瓦櫓跡からは眼下の宮川を越えて東方向の眺望が広がっています。東辺石垣を外側から見上げつつ北端まで進むと、石段を下った右手に十二番門跡がありました。
石段を戻り月見櫓の麓を回り込んで十一番門跡から再び本丸に入ると、本丸北端には東側に小天守とも呼ばれた粟積櫓、西側に大戸櫓と長屋櫓が建ち並び、各櫓跡からは北方向の眺望が開けていました。
さて、これで本丸をひとめぐりしたので、搦手側に下りていきます(続く)。
+ 続きを読む