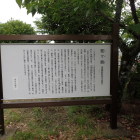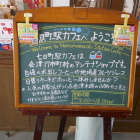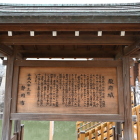本丸堀の脇を通って、2023年に続き本丸の発掘現場を見学してきました。きゃっしるもちょこっと覘いていきます。駿府城の見どころである二ノ丸水路を確認してから、お目当ての静岡市歴史博物館の企画展「十返舎一九と蔦屋重三郎」へと向かいました。この企画展だけだったら150円の料金。国会図書館所蔵の吉原細見、朋誠堂喜三二作「見徳一炊夢」、恋川春町作「金々先生栄花夢」などが惜しげもなく並べられていてびっくりしました。トーハクの特別展のような混雑もなく非常に満足度の高い企画展でした。静岡市歴史博物館に寄託されている「東海道中膝栗毛」ももちろん拝見してまいりましたとも。その後は、県庁別館21階の展望フロアより、駿府城の俯瞰も楽しんできました。
+ 続きを読む