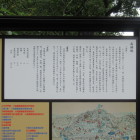竹中重利の続き(2/2)です。大分府内城は大友氏改易後の1597年、秀吉の命で府内(大分市)に入った福原直高(石田三成の妹婿)により、新たに築城された城です。故に大友氏とは全く関係のない城なのでお間違えなきよう。 直高はここに天守台を築きますが(写真③④)そこで1600年関ケ原へ出陣。西軍として大垣城の守備を任されますが、敗北し自害してしまいます。
関ケ原後の1601年、豊後高田から竹中重利が入り、直高が築いた天守台の上に四重の天守を建てました。ちょっと遊び心で想像図を作り妄想してみました。こんな雰囲気だったのではないでしょうか?(想像図⑩🤔)。
重利は内々堀・内堀・外堀と三重の堀を築き、内堀の外側の山里丸(現:松栄神社)に御殿を建て、御殿と本丸を廊下橋でつなぎました(写真⑤)。重利の頃は、北は海で東は大分川がある三角州に本丸があり、その本丸の北東側に天守がある悌郭式の縄張りだったようです。そして外堀で囲むように城下町を築いていきました。
その後1634年に下野国壬生より入った日根野吉明により、内堀に沿っての櫓や塀が白漆喰で塗られ、現在のような城の風貌が完成します。しかし、その後に入った大給松平氏の1743年に天守は火災で焼失、その他も1945年太平洋戦争の大分空襲で人質櫓と宗門櫓以外は全て焼失してしまいました。戦後から徐々に復興され、平成8年には廊下橋も再建されました(写真⑤)。
現在は大分城址公園となっていて、市民の憩いの場になっています。令和5年の豪雨で西ノ丸の石垣が壊れましたが、現在発掘調査を行いながらゆっくりと修復されているようです(写真⑥)。文化会館跡地も整備計画が示されていました。
重利は1615年54才で没し、松栄神社の傍らにある浄安寺に眠っています(写真⑨)。私は天守台に立ち、ぐるりと眺めてみました(写真⑦⑧)。四重の天守を完成させた重利は、どんな思いで天守からこの景色を眺めていたのでしょうか? 関ケ原以降、戦のない平和な世になった事に感謝しながら、そこから没するまでの約10年間、家督は子の重義に譲り、のんびりとここで・・・余生を過ごしていたのかもしれませんね。
+ 続きを読む