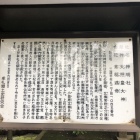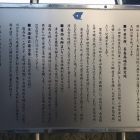(前に出てくる退会済みユーザーともじがいっしょなのは
退会済みユーザーが私だからです
くわしくは私のサイトを開いてみて下さい)
まだ小さい頃に行った首里城
初めて行った城です。
首里城のスタンプラリーを1時間かけてやりました。
スタンプラリーに熱中で城のことは覚えていません。
そのはなしをかえてしまうけど
首里城火災(2019/10/30)全焼してしまった、沖縄のシンボル首里城
早く復興してほしいです
写真は2017年のものですのものです。
人が映っていますがご了承ください
+ 続きを読む