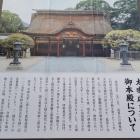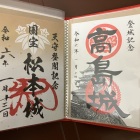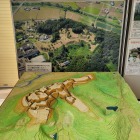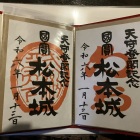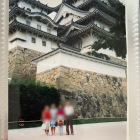佐奈田霊社の周辺は治承4年(1180)源頼朝が平氏追討のために挙兵し平家方と戦った石橋山古戦場とされています。頼朝軍300に対し平氏側は大庭景親ら3000であったため衆寡敵せず頼朝軍は劣勢に立たされ、頼朝側の佐奈田(真田)与一義忠は討死し与一の郎党・文三家安も主の後を追うように討死したそうです。与一が討死した場所に与一塚が建てられ、佐奈田霊社には与一が祭神として祀られています。
与一塚から100mほど行ったところに文三を祀る文三堂があります。
建久元年(1190)伊豆山神社に参詣した頼朝は帰途の際、この地を訪れ二人の忠節を偲び涙を流したと伝えられています。
+ 続きを読む