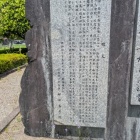主郭前の小山は写真だけでは解りづらいですが、かなりの高さがあります。小山の角度は急で、下に深い堀切があり、岩も所々にむき出しになっています。しかもこの小山に沿って踏みしろのような道が付いています。この踏みしろが、いつの時代のものか解りませんが、これは「釣り」と考えた方が良いでしょう。うかつに攻めて足をすべらして、そのまま堀に落ちたら大ケガです。
西側(右手)にそって迂回していくと、小山や主郭に沿って側道が付いていて、ここから小山の裏側に登ることも出来ます。そこを登ると深い堀切が有りますが、まずは主郭を先に攻めることにします。
写真だけでは解りづらいですが、側道と主郭の高低差は結構あります。なかなか登りやすい場所が見つからなかったので、南端から登ることにしました。登った先は激ヤブで、行けども行けどもヤブシダが続きます。郭の中央部分まで行って、主郭攻略終了とします。
郭の端から下に降りたい所ですが、なかなか良いポイントが見つかりません。
人が重力に逆らえるのは、せいぜい1mちょっとなので、膝等に負担をかけずに降りれるポイントを探します。踏みしろも途中で消えていたりするので、降りては登ってを繰り替えして、結局南端に戻ってそこから降りました。
+ 続きを読む