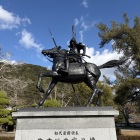観音寺城は近江守護佐々木六角氏が戦国時代に居城とした、標高433mの繖山山頂から南山麓にかけて郭が広がる大城郭で、中世五大山城の一つとして数えられています。
観音寺城の特徴は石垣を多用している事です。石垣の本格的な導入は安土城以後のこととされており、安土城より古い観音寺城の石垣の多用は例外的で、戦国時代としては唯一の城とのことです。
観音寺城には、6度目の訪問で山頂から南西に延びる伝本丸・伝平井丸・伝池田丸・大石垣を見学し、満足していましたが、前回訪問した折、安土城考古博物館の学芸員の方から、繖山山頂から東に延びる尾根筋にも見どころがたくさんある事をお聞きし、今回訪問してきました。
今回、朝7時登頂者用駐車場に駐車(無料)、徒歩で伝布施淡路丸・繖山東尾根筋をへて山頂へ、山頂から南西に延びる尾根筋の伝本丸・伝平井丸・伝池田丸をへて大石垣へ、帰りは伝平井丸から伝本丸に入り、本丸虎口から山頂に延びる尾根筋を通過し、来た道を引き返し、伝目加田丸から結神社へ、結神社から登頂者用駐車場へ。その後、石の寺 教林坊で庭園を鑑賞し、教林坊から徒歩で御屋形跡へ(天満宮)14時過ぎに帰路へ着きました。
たっぷり観音寺城を堪能しましたが、まだまだ繖山には遺構が眠っていると思われるので、また訪問したいと考えています。
+ 続きを読む