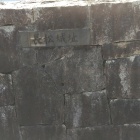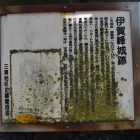【岩屋城】
<駐車場他>第一駐車場5台分程度、第二駐車場20台分程度あり。
<交通手段>車
<見所>曲輪切岸・堀切・畝状竪堀群
<感想>現地説明板によると岩屋城は1441年に山名教清が嘉吉の乱の論功行賞により美作国の守護に任ぜられた際に築城されたとされます。その後赤松氏や浦上氏、その家臣が裏切って尼子氏に付いたりして混沌とした勢力下において城主が変わりますが、戦国時代後半には宇喜多氏の支配下の城となります。1581年に宇喜多氏が毛利氏を離れ織田氏に付いたことから岩屋城は毛利氏に攻略されます。1582年の備中高松城の戦い終了後に領土の境目を高梁川とするが、それより東側にいた美作の毛利氏の諸将が抵抗します。岩屋城の周囲に包囲する陣城跡はこの時の宇喜多氏による武力接収戦による籠城攻めの跡と思われます。その後調停により再び宇喜多氏の城として戻り、宿老の長船貞親の城となりますが1590年に野火により焼失し廃城となったようです。
第一駐車場に説明板と登山道見学コースの案内板があります。第一駐車場脇に登山口があり城跡を一巡りして第二駐車場に出るルートになっていますが、第一駐車場から登ると遊歩道にはなっているものの、主郭まで1000m程の登山となりますので、お勧めは登山道見学コースの逆走、第二駐車場から舗装道を登っていくのが楽だと思います。
城跡へは見学コース順に、慈悲門寺砦跡、ここは本郭以外はかなり藪化して東西にある曲輪群を散策するのは難しいです。本郭には中心に堀か庭園跡の石積みの仕切りがあります。最奥に坊跡かの土壇の土盛があります。次に山王宮跡、ここは巨岩壁の岩窟に権現様を祀った祠があります。明治初期まで祠で一杯だったそうです。拝殿跡には土台の石積みが残ります(江戸時代のものかも)。
城跡は見学コース順に門跡⇒人工の龍神池⇒三の丸は3段の連郭⇒馬場の帯曲輪を通り馬場曲輪⇒主郭⇒二の丸は小さい尾根曲輪⇒二の丸北東部の大堀切はでかくて見応えあり。⇒城跡の北東側にある「手のくぼり」という畝状竪堀群は現地に十二条とありますが、実際数えてみて、表面観察できるのは八条でしたが、かなり見応えありました。そこから急坂の舗装道を降りて第二駐車場に至りますが、舗装道なので先に記述した逆走ルートの方がよかったかもと思ったわけです。大堀切、畝状竪堀、主郭を中心に馬蹄形状の連郭が見応えある素晴らしい城跡でした。私の先の投稿で宇喜多氏軍の陣城群の一つ、荒神の上砦(城びと未登録)にも行ったので御参考にしてもらえれば。陣城も全て巡ると1日楽しめる城跡群です。
この日は2024年新年最初の日帰り城跡巡りとして、満足度の高い城跡ばかりで楽しめました。518㎞無事走破。
<満足度>◆◆◆
+ 続きを読む