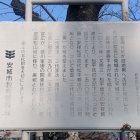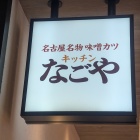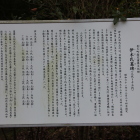皆さま、新年あけましておめでとうございます。
さて、今年も「城めぐり一年の計」を立てるにあたり、まずは昨年の振り返りから。
〇 1.金森長近ゆかりの城めぐり
✕ 2.資料館・博物館に行く
△ 3.日本100名城かるた大会に出る
「金森長近ゆかりの城めぐり」は飛騨遠征などおおむね達成できた(残り数か所のみ)ので〇、「資料館・博物館に行く」は途中からそんな一年の計を立てたことすら忘れていたので✕、「日本100名城かるた大会」は開催されませんでしたが、その代わりに赤色立体地図お城かるたのかるた取り体験には参加できたので△で。
ということで、今年の城めぐり一年の計は…
1.豊臣秀長ゆかりの城めぐり
今年の大河ドラマ「豊臣兄弟!」にちなんで秀長ゆかりの城めぐりを。秀吉だと全国きりがないですが、秀長だけなら何とかなるかな、と。日向遠征(高城、根白坂の戦い)もしたいところですが…。
2.「松阪市内の城めぐり」「金森長近ゆかりの城めぐり」の完遂
一昨年の「松阪市内」と昨年の「金龍紀行」の取りこぼしの回収も。特に松阪市の阪内城は、電気柵に阻まれて断念していましたが、昌官忠さんが当然のように登城しておられるので通れるようになったのかな、と。
3.城びと投稿をさぼらない
城びとへの投稿が半年遅れになってしまっているので、今年は「下調べ(予習)して城に行き(実行)、城びとへの投稿(復習)により理解を深める」というルーティーンをしっかり守ってやっていきたいと思います。…でも、追いつけるのかなぁ(弱気)
…というような感じで一年やっていきたいと思っていますので、本年もどうぞよろしくお願いいたします。
+ 続きを読む