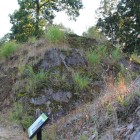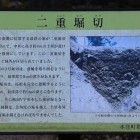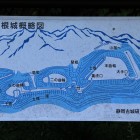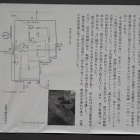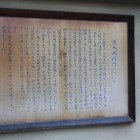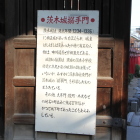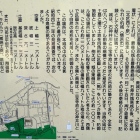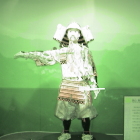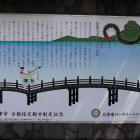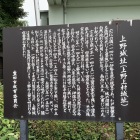迷いに迷い、なかなかたどり着けなかった「戸張城」。
相馬氏初代当主、相馬 師常さんの三男 戸張 行常さんの居城のようです。
前回、「布施城」の投稿で相馬氏と千葉氏が一族だった事が分かりました。
一方、平将門さんの子孫も相馬を称していると投稿しましたが、養子やら結婚やら複雑に結びつき千葉氏も、絡まってました。
『人間みな兄弟』、、、古っ!(笑)
相馬子孫問題、勝手に落着します。
「戸張城」の所在地も複雑で、文京区立 柏学園の敷地内です。
千葉県なのに、東京の区立学校??
調べてみると、校外学習等で使われていたようです。
現在は閉鎖してます。
柏市から千葉市方面の国道16号を車で走ると左手に、うっそうとした小山が見え、大津川まで行ってしまったら行き過ぎです。
この、小山が「戸張城」のようです。
小山方面に左折する道がトンネルを出てすぐなので、曲がりづらく、行ったり来たりを繰り返しました。
もう、大津川に下りの畑道から攻城です。
車を路駐して、学園に通じる坂道を歩き正門(?)に到着しました。
頑丈に鍵がかかっていて入れません。
いやいや、鍵が かかってなくても、建物が見えるので入れません、、、怖くて。
写真は全てフェンス越しです。
「戸張城址公園」にならないかなぁ。
手を加えなくても、お城好きには、大好物なそのままの遺構が見えましたから。
+ 続きを読む