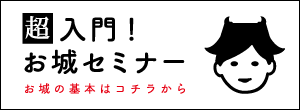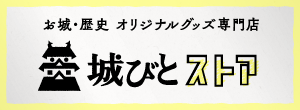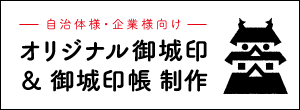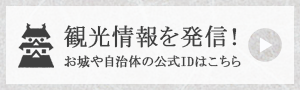2022/03/16
マイお城Life 【直木賞受賞記念!】小説家・今村翔吾さん[前編]史実をつないでフィクションを紡ぎ出す
2021年下半期の直木賞に『塞王の楯』(集英社)が受賞しました。穴太衆の石積み職人を主人公に、関ヶ原の戦いの前哨戦となった大津城攻防戦を描いた500ページを超す大作です。受賞発表の際には涙も見せた作者の今村翔吾さんの特別インタビューを前後編でお届けします。前編では、作品にかける思いや『塞王の楯』制作の舞台裏をお伺いしました。

第166回直木賞を受賞した今村翔吾氏の『塞王の楯』。「なぜ人は争うのか」、その根源的な問いをテーマにしている
穴太衆は戦国時代の「守る」の象徴
『塞王の楯』は、石工職人と鉄砲職人の視点から戦国時代の攻城戦を描いた歴史エンタメ小説である。主人公は自らも戦災によって家族を失った、穴太衆(あのうしゅう)※の若き頭領となる飛田匡介。そのライバル役として、国友衆(くにともしゅう)を率いる国友彦九郎が登場する。穴太衆とは寺院や城郭の石垣づくりを専門とした石工集団、国友衆は戦国時代に広まった鉄砲製造を生業とした鍛冶集団で、どちらも近江国(現・滋賀県)を本拠にしていた。
戦国時代を題材にした小説は無数にあるが、作品の中心に職人を据えるというのはめずらしい。今回、穴太衆に注目したのはどんな理由だったのか?
(今村)
僕が小説を書き始める場合は、まず大きなテーマを決めてから、逆算的にどの時代を扱うか、どの視点で作品をつくれば一番このテーマを伝えられるかということを考えます。はじめに「織田信長」を書きたいとか、「本能寺の変」を書きたいというのはあまりありません。
今回の小説では、「人間同士の争い」というのがテーマにありました。「戦争はなぜ起こるのか」、「人は望んでいないのになぜ争うのか」ということを書きたかったんです。そのテーマから本書の「守る対攻める」という設定を考えたとき、攻める側は雑賀衆でも甲賀衆でも何でもいけるなと思ったのですが、守る側ははじめから穴太衆一択でした。石垣や穴太衆の存在というのは、戦国時代の「守る」の象徴みたいなものですよね。
じゃあ穴太衆と対になる攻める側を考えていくと、雑賀衆や甲賀衆は戦闘を専門職とする傭兵であり、それよりも穴太衆のような職人集団のほうがいいなと感じました。そこで閃いたのが鉄砲職人である国友衆です。穴太衆も国友衆も同じ近江にある職人集団であり、琵琶湖をはさんで対岸に位置しています。「これはいけるぞ」、と。こうして、「穴太衆対国友衆」という構図が決まりした。
——今村さんは現在、滋賀県にお住まいですよね。近江を舞台に書きたいという思いはなかったんですか?
(今村)
それ、よく聞かれるんですけど、ぶっちゃけ、そういう気持ちはないんですよ(笑)。石田三成を主役にした『八本目の槍』(新潮社)の舞台も近江でしたが、それも近江だから取り上げたというわけではありません。「戦国時代の青春を描きたい」というテーマが先にあり、「でも七本槍だとまっとうすぎるから、その枠から外れた三成がいいかな」という感じで設定が決まっていきました。
ただ結果的に、近江を取り上げることが多いのは事実です。近江は京都の隣にあって交通の要衝ですし、だからつくられた城の数も日本一と言われています。関ヶ原の戦いは美濃(岐阜県)でしたけど、例えば壬申の乱とか、天下の帰趨(きすう)を決める重要な戦いが近江で起こった例も多いですよね。穴太衆や国友衆などの技能集団が育つ土壌もあった。それだけ、近江が歴史的に重要な土地だったということでしょう。
※穴太衆については、こちらの記事「超入門! お城セミナー 第48回【歴史】「穴太衆(あのうしゅう)」ってよく聞くけど何をした人たちなの?」(https://shirobito.jp/article/634)もご参考ください。
職人への取材がリアルな描写につながる
本作の主役である穴太衆は、比叡山のお膝元であり日吉大社の門前町でもある近江国穴太、現在の滋賀県大津市坂本の地で発達した。古くは古墳の築造を行っていた集団の末裔ともいわれ、中世には寺院の石組みなどを生業とし、織田信長が総石垣の城を創意して以降、城郭の石垣づくりの中心的存在になったと伝承される。(ただし、実際に穴太衆が手がけた城や城郭史における穴太衆の役割については文献上定かではない)
この穴太衆の技術は現在にもしっかりと伝わっており、代表する職人のひとりに15代目当主の粟田純徳さん(粟田建設社長)がいる。今村さんは『塞王の楯』の執筆にあたり、この粟田さんにも取材したという
——粟田さんの取材ではどんなことを聞かれたんですか?
(今村)
たくさんお話をうかがいましたよ。石垣に関する話が中心ですけど、好きな食べ物とか関係ない質問もぶつけたりして、本当にお世話になりました。
取材の中で1番印象的だったのは、手の感覚を研ぎ澄ますために、塩で手を洗うという話ですね。職人さんの手ってゴツゴツしているイメージがあるじゃないですか。でも、実際に見せてもらいましたけど、塩で手を洗うおかげで、みなさん異様に手がキレイだったんです。高い化粧品を使わなくても、塩でいいじゃんって思っちゃいました。
あと、これも小説内で書かせてもらいましたけど、匡介や源斎(匡介の師匠)が小石をピシピシと石材に投げ当てて次に積む石を指示するという行為も、粟田さんから聞いた話です。ちょっと高いところから小石を投げて、「次これ、次これ」って指示するなんていかにもフィクションぽいのですが、粟田さんのおじいさんが実際にやっていたそうですね。ただ、「誰でもできることじゃない。できるのはおじいさんだけやった」ともおっしゃっていました。それで作中では、匡介の職人としてのひとつの到達点を示すために、このシーンを使っています。
小説内では書けませんでしたが、「隅石(石垣のコーナー部分。巨石が用いられることが多い)を崩されるのが穴太衆にとって1番の屈辱」だとおっしゃっていたのも印象深いですね。隅石を壊されたら、そこの石垣すべてを壊されたこととイコールなのだそうです。
——作中では同じ石工集団の中で、石材を山から切り出す「山方」、石材を石積みの現場まで運ぶ「荷方」、運ばれた石材を積み上げる「積方」に役割分担されています。この分担も取材で得られた知見でしょうか?
(今村)
そうですね。粟田さんの話だと役割分担はされていただろうし、実際に「山方」「荷方」「積方」と呼ぶとのことでした。この中で、「山方」と「積方」が何をする人たちなのかは何となくイメージがつきますよね。でも、「荷方」は「ただ運ぶだけじゃん」って思われがちで、その苦労がいまいち伝わりにくい。そのため作中では「玲次」という荷方を専門とするキャラクターを出して、荷方の役割が埋もれないように工夫しました。
ただ、石垣づくりの工程や役割分担については、史料が残っていないので具体的にはわからないというのが実状です。それだけに千田嘉博先生から、「本書で書かれている職人の役割や作業工程は大枠で間違っていないんじゃないか」と言ってもらえたときは安堵しました。城郭研究の分野でも石垣づくりについては特にわからないことばかりらしいので、研究が進むことを期待しています。

「小説を読んで城に行きたくなったと読者に言われことが本当に嬉しい」と語る今村氏。ちなみに、ご自身が今1番行きたい城は弘前城だとか
きちんと史実をつないでフィクションを紡ぎ出す
『塞王の楯』のクライマックスでは、国友衆の国友彦九郎がつくった「至高の矛」と、穴太衆の飛田匡介が築いた「最強の楯」が大津城攻防戦で激突する。大津城攻防戦は天下分け目となった関ヶ原の戦いの前哨戦で、東軍についた京極高次の居城・大津城(滋賀県大津市)を、毛利元康や立花宗茂らの西軍が攻めた戦いだ。作中、京極軍と穴太衆は一致団結して、数倍の敵と手に汗にぎる攻防戦を繰り広げるのだが、そこでは石垣技術を用いたあっと驚く戦法が次々と展開される。「石垣を使った戦法」がどんなものか、気になった人はぜひ本書を読んでいただきたい。
さて、大津城攻防戦は関ヶ原の戦いの結果を左右した合戦だったが、一方で登場する武将はやや地味で、そこまで有名な戦いとはいえない。なぜ、本書のメイン舞台を大津城にしたのだろうか?
(今村)
消去法で大津城が残ったというのが正直なところです。大筒(大砲)が重要なアイテムになりますが、実際に大筒が使用された戦いって数が限られますし、条件が合わないんです。例えば、大友宗麟が「国崩し」(フランキ砲)という大砲を使ったっていいますけど、あれはヨーロッパからもたらされたもので、国産ではありません。豊臣が滅ぼされた大坂の陣も頭をよぎりましたが、大坂の陣で用いられた大砲は堺の職人が製造した芝辻砲で、国友の大筒ではない。
大津城で使用された大筒が国友衆のものかどうかは定かではないのですが、その直後の関ヶ原の戦いで石田三成が大筒を戦場に並べさせたという記録が残されています。それであれば同じ西軍ですし、大津城で用いられたのも国友製だろうとなり、自然と大津城に行き着いた感じですね。
——大津城は完全に埋め立てられた城で、遺構と呼べるものはほぼ残りません。執筆するのに難しかったんじゃないですか?
(今村)
いや、逆に何も残っていない分、想像を膨らませることができたので、意外と書きやすかったですね(笑)。大津城は水城で、縄張り(城の構造)も独特じゃないですか。縄張り図を見たとき「これはイケるな」と思い、そこから攻防を組み立てていきました。
作中で、大津城の外堀に琵琶湖から水を引くシーンがありますよね。だけど、大津城の外堀が水堀だったかどうかはよくわかっていないんです。現在は民家が建っているため発掘調査も難しくて、「外堀が水堀だったかどうか」論争は決着がついていません。でも、じつは金沢城で同じように標高の高い堀へと水を引く土木工事が行われていますので、「じゃあできるやろ!」と、勢いで水堀にしてしまいました。匡介が説明する「水が逆さに流れる」方法は、この金沢城の工事技法を応用したものです。でも書いておいてなんですが、本心では「水堀じゃなかったんじゃないか」とも思っています(笑)。
小説はフィクションですけど、技術的な部分ではウソはつきたくなかった。だからこの外堀に水を引くシーンでも、どれほど掘ればいいかとか、じゃあその土木工事は何日かかるかとか、編集者といっしょに必死に計算して検証しましたね。僕はあまり数学は得意じゃないのですが……。大筒の砲弾はどんな角度だと天守に届くのか、みたいな計算も何年ぶりかでサイン・コサインとか持ち出して計算しました。

大津城跡。城びと投稿写真(イオさん)より
——史実かどうかでいうと、国友衆が鋼輪式の鉄砲を製造していますが、あれは史実なのでしょうか?
(今村)
確実に史料に残っている記録としては、大津城の戦いから約30年後に日本国内でも鋼輪式の鉄砲がつくられています。そこでつくられた鉄砲は軍事的なものではなく、芸術工芸品的なものだったようですが。でも技術的につくれることはつくれた。記録として残っていないだけで、もしかしたら30年前にもあったのかもしれない、ということで登場させました。鉄砲の進化を示せるような素材がどうしても欲しかったというのが、鋼輪式を登場させた1番の理由です。
フィクションという点では、職人たちが総動員で石垣を修復する「懸(かかり)」と、石を集積する場所である「流営(りゅうえい)」という言葉は僕の創作ですね。特に「懸」のほうは、前線に立つ石工集団の決意といったものを読者に伝えるために、どうしても言葉をつくる必要があったんです。
造語をつくっちゃうというのは、師匠とあおぐ池波正太郎先生も得意としていました。「懸」という言葉ではなかったかもしれませんが、きっとこういう行為はあっただろうと確信しています。小説を創作にするにあたり、歴史の中から魂の部分を引き取って、あったであろう行為に名をつけられるというのは、小説家の特権でもありますし、1番楽しい部分ですね。

今村翔吾・著『塞王の楯』/集英社
[書 名]塞王の楯
[著 者]今村翔吾
[版 元]集英社
[刊 行]2021年10月
『塞王の楯』特設サイト https://lp.shueisha.co.jp/tatexhoko/
<プロフィール>
今村翔吾(いまむらしょうご)
1984年京都府生まれ。滋賀県在住。ダンスインストラクター、作曲家、埋蔵文化財調査員を経て、2017年作家デビュー。
主な作品と受賞歴に短編「蹴れ、彦五郎」(伊豆文学賞)、短編「狐の城」(九州さが大衆文学賞大賞・笹沢左保賞)、『童神』(角川春樹小説賞)、『八本目の槍』(吉川英治文学新人賞、野村胡堂文学賞)、『じんかん』(山田風太郎賞)、『塞王の楯』(直木賞)など。ほかに「羽州ぼろ鳶組」シリーズ(吉川英治文庫賞受賞)、「くらまし屋稼業」シリーズがある。2021年に大阪府箕面市の書店「きのしたブックセンター」に出資しオーナーとなる。
▼インタビュー後編はこちらから! https://shirobito.jp/article/1523
執筆:かみゆ歴史編集部(滝沢弘康)
「歴史はエンタテインメント!」をモットーに、ポップな媒体から専門書まで編集制作を手がける歴史コンテンツメーカー。手がける主なジャンルは日本史、世界史、美術史、宗教・神話、観光ガイドなど歴史全般。城関係の主なの編集制作物に『よくわかる日本の城 日本城郭検定公式参考書』(ワン・パブリッシング)、『完全詳解 山城ガイド』(学研プラス)、『廃城をゆくベスト100名城』(イカロス出版)などがある。