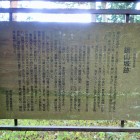鍋山城は3つの山によって構築され、大鍋山山頂に本丸、小鍋山山頂に二の丸、下鍋山に出丸は配されています。本丸は標高752mの山上にあり、東側と西側に石垣が現存しています。鍋山城の築城については、飛騨の小領主鍋山氏が築城したが、飛騨南部で勢力を増していた三木氏にくだり、鍋山城は三木氏のものとなっています。
その後、本能寺の変を経て、羽柴秀吉公が天下を平定しようとしていたが、三木自綱公はこれに従わず、佐々成政公と組んだ為、秀吉公から命を受けた金森長近公の攻撃を受け三木氏は滅んでいます。秀吉公から飛騨を与えられた金森氏は最初この鍋山城を本拠としましたが、広い土地が無く、交通の便も悪かった為、高山城を築城し、鍋山城は廃城となっています。
この日、webで大地震が起こると予言されており、信じてはいなかったが取り合えず山の方へ行ってみるかと思い、前から「行ってみたい」としていた鍋山城へGO。東海北陸道を飛騨高山を目指し北進、高山市漆垣内の四天王神社をナヴィにセットし、迷わず登城口へ。
登城口から中々の急坂を登ること20分程で主郭部に到達できます。
+ 続きを読む