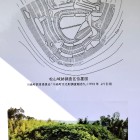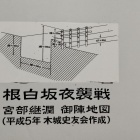私が高城を訪れたのは今回で3度目ですが、今回の目的は高城ではなく、直線距離で東に1kmの所にある、豊臣秀長が最後に陣を敷いたとされる「松山(松山之陣跡)」です。
また高鍋駅から木城行のバスに乗り30分、終点「木城温泉館湯らら」で下車すると目の前に松山が見えました(写真①の左の山)。標高は100mくらいです。な~んだ楽勝じゃないか😊と思いきや・・・?
この一帯は大きな戦いが2度あった場所である事は、みなさん御存知と思います。2度とも高城に籠る薩摩の山田有信を攻めた戦いです。1度目は1578年に大友軍が攻め、救援に来た島津全軍と決戦した「高城川の戦い(耳川の戦い)」です。大友軍はこの松山に陣を敷きますが、眼下の高城川にて致命的な大敗を喫してしまいます。
2度目は1587年、九州征伐で東ルートを任された豊臣秀長が15万の大軍で出陣し、この松山に陣を敷き高城に籠る山田有信を攻めます。そして有信を救援に来た島津全軍と対決した「根白坂の戦い」です。ここで島津軍は致命的な大敗を喫し、島津義久は豊臣秀吉に泰平寺にて降伏します。
目の前なのに、どうやらこの温泉館から直接登れる道は無く、山の東側からぐるりと8の字に遠回りして登り、絶景橋を渡れば上まで行けるようです(図④)。結局遠回りして歩き続け1時間もかかってしまいました(往復2時間)。車の方は宗麟原に駐車場があります。TVを見ると各地寒波による大雪で大変な映像が流れていましたが、ここ宮崎県は別世界。快晴で気温12度、川には菜の花が咲き、頂上に着く頃には汗が流れ出し、本当に今は1月なのかと疑いたくなる程の暖かさでした(写真②③)。雪国の方にはすいません。
そして橋を渡って宗麟原入口に着くと説明板がありました(写真⑦⑧)。そこから左側の松山へ入ります(写真⑨)。入った先は竹藪だらけで全く整備されておらず眺望もなく、藪をかき分けて行ける所まで進みました。するとちょうど切堀の跡を見つける事ができました(写真⑩)。写真⑧の図の南北の曲輪と曲輪を遮断している切堀と思われます。しかしそこから先は藪がひどくて前へ進めず、結局ここで断念してしまいました。もう少し整備してほしいものです。
それから絶景橋へ戻り、全体を見渡して見ました(写真⑥)。実際の決戦は、ここから遠くに見える「根白坂」で行われました。秀長はどんな思いで、この松山之陣から根白坂の戦況を見つめていたのでしょうか?
私は前回、がんばって高城から往復5時間かけてあそこに見える根白坂まで歩き、そして「なぜ島津は豊臣に敗れたのか?」を追いました。その時の様子は(お城を探す→高城)から検索して、(関ケ原の26人)の78・79・80話で詳しくレポートしていますので、もし興味のある方はそちらを読み返していただければと思います。
根白坂の戦いで勝利し大和郡山城へ戻った秀長は、その後に病で倒れます。それゆえ小田原征伐には参陣できませんでした。そして3年後、そのまま大和郡山城にて生涯を閉じてしまいます。
つまりこの場所は、豊臣秀長が最後に出陣し戦をした場所だという事になります。大河ドラマ『豊臣兄弟』では、この根白坂の戦いがどのように描かれるのか?🤔 そして終盤のクライマックスとなるのか?(😱~)。私は今から密かに楽しみにしています!😊
+ 続きを読む