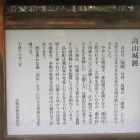興福寺一乗院方衆徒の鷹山氏が室町期に築いた城で、戦国期には畠山氏、次いで松永氏や筒井氏に従い、筒井定次の伊賀転封に伴って廃城となったと考えられます。
北側の登城口前に駐車して登城開始。登城口からは遊歩道が城域の東側を回り込むように整備されていて、8分ほどで九頭龍王社を祀る十三重塔が建てられた南西曲輪に到達。南西曲輪には高山城跡の説明板が立てられており、手持ちの縄張図がなければここが主郭かと思ってしまうところでした。南西曲輪の北面には竪堀らしき地形が見られますが、後世のものと考えられるようです。南西曲輪から谷を挟んだ南側には出曲輪があるようですが、南に下りる道は立入禁止になっていたので断念し、遊歩道を北に外れて主郭部に向かいます。
主郭部は主郭と周囲の曲輪群からなり、主郭の北辺には櫓台状の土塁が、南西部には井戸跡らしき窪みがあります。櫓台から北裾に下りて行くと鞍部に浅い堀切が設けられていました。堀切の西側には竪堀状の地形が見られますが、こちらも後世の改変または自然地形のようです。堀切から東側に回り込むと、主郭部東側の帯曲輪北端に土塁を設けて北側からの侵入を阻んでいます。帯曲輪の南端から上った先の主郭部南東の曲輪は水道施設により改変されていました。南東端の虎口も水道施設建設時に改変されたものかもしれません。そして主郭部の曲輪群に三方を囲まれた南帯曲輪で主郭部をひとめぐり。
南出曲輪に行けなかった上に、いろいろと改変を受けていて、城自体にはあまり見応えはありませんでしたが、あれこれ調べてみると、多聞山城の戦いで焼失した東大寺大仏殿の再建に尽力した公慶上人は鷹山氏の出であることや、帰農した鷹山氏旧臣が作った茶筅が高山の伝統工芸品として現在も茶筅の全国シェア80~90%を占めているなど、鷹山氏の存在は意外なところで現代に影響を与え続けているんだな…などと、むしろ城以外のほうが印象的でした。
+ 続きを読む