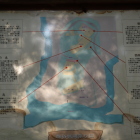鎌倉時代後期から戦国時代にかけて櫨谷地域を治めた衣笠氏の居城です。戦国時代に羽柴秀吉が三木城を攻めたときに別所方に味方し、三木城落城の頃に落城したと伝えられています。
丘陵の尾根に築かれた城で、堀切で区画して防御しています。本丸、二の丸は整備されていて三の丸は満福寺となっています。二の丸と三の丸の間に堀切がありますが、満福寺近くの登城路から進むと倒木などで見づらい状態でした。本丸の北側にも深い堀切が残っています。ぴーかるさんの投稿を参考に西の壇よりアプローチするとその堀切の底部に行くことができました。西部は容易に散策できますが、北側は倒竹で侵入が困難になっていました。西側は竪堀となって落ちています。ただ谷のような地形が隣にあり二重掘りのようにも見えました。「山城賛歌」さんのブログにある縄張りを見ると二重掘りのように描かれていましたが、自分としては城内に見ることができる縄張り図よりしっくりします。
眺望はよく二の丸から瀬戸内海が見えました。
コンパクトながら見ごたえのある遺構が残っています。
+ 続きを読む