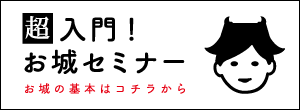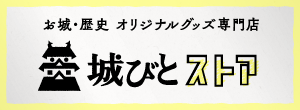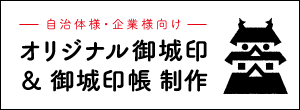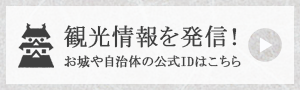2019/11/20
昭和お城ヒストリー 〜天守再建に懸けた情熱〜 第10回【首里城】琉球・沖縄の魂は五度よみがえる
昭和という時代にスポットを当て、天守再建の背景にある戦後復興や町おこしのドラマに迫る「昭和お城ヒストリー」。令和元年10月31日(木)未明に発生した、首里城火災。火災に見舞われ炎上する首里城の映像はたいへんショッキングでしたが、首里城はこれまで、ときに火災に、ときに戦災に見舞われながら、再建を繰り返してきました。沖縄の人々に寄り添ってきた首里城の歴史を振り返ってみましょう。

鮮やかな朱色に彩られ首里城正殿(写真右)と北殿(左)。2019年10月31日の大火災で残念ながら焼失してしまった
令和元年の火災が首里城にもたらした被害の爪痕
日本の城郭で、また痛ましい被災が発生した。沖縄を象徴する存在の首里城が全焼したのである。読者の多くは、早朝のテレビ、またはネットニュースで知ったのではないだろうか。著者も起き抜けにつけたテレビ画面で、紅蓮の炎に包まれる正殿の映像を見せつけられ、寝ぼけた頭ではことの次第を理解できず、意識が覚醒するとともに、事態の深刻さに青ざめてしまった。
火災が起きたのは10月31日午前2時半ごろ。正殿北側1階の分電盤が出火元と見られ、午後1時半に鎮火したときには、北殿や南殿など7棟の貴重な建造物が焼失していた。焼損した面積は4836平方メートル。消火活動に11時間もかかったのは、出火が深夜だったことや施設の不備により初期消火が遅れたことに加え、高台に建ち城壁が巡るという、城ならではの構造が消火活動をさまたげたという理由もあった。建造物とともに、宝物や歴史資料の被害も深刻である。首里城を管理運営する沖縄美ら島財団によると、琉球王朝時代の美術工芸品など、所蔵品約1500点のうち、4分の1以上にあたる400点強が被害を受けた可能性があるという。
さて、多くの報道で述べられていたとおり、首里城はこれまで1453年、1660年、1709年、1945年と4度焼失の憂き目にあっており、今回の火災で被害を受けた建造物はいずれも復元建物であった。そのため、首里城は「琉球王国のグスク及び関連遺産群」として世界遺産に登録されているが、世界遺産となったのは地下の遺構にあたる「首里城跡」であり、復元された建物は構成遺産に含まれてはいない。
焼失と再建を繰り返す、首里城の波瀾の歴史を振り返ってみよう。

龍潭から見たライトアップに映える首里城。これらの建造物の多くが、火災により失われてしまった
「鉄の暴風」と呼ばれた爆撃により炎上
首里城は、琉球・沖縄の歴史そのものである。
1429年に琉球を統一した尚巴志(しょうはし)が首都を首里に定めて以降、明治政府に城が明け渡された1879年まで、450年間にわたり琉球王国の王城であり続けた。江戸時代になると、琉球は徳川幕府を後ろ盾とする薩摩藩に従属し、かつ中国・清朝にも臣下の礼をとる二重支配体制下に組み込まれながらも、王国として独立を保ち続けた。琉球の置かれた微妙な政治状況は、中国からの使節を迎え入れた北殿と薩摩の役人を接待した南殿が御庭(うなー)をはさんで対峙している、首里城の構造にも如実にあらわれている。
明治に入ると琉球は日本に組み入れられ(琉球処分)、「沖縄県」が設置された。王城としての役割を失った首里城は陸軍の兵舎となり、その後は学校として利用された。当時、建造物や遺構は荒れるにまかせた状態だったという。大正12年(1923)には解体撤去が決定していたが、その中止に尽力したのが香川出身の鎌倉芳太郎だった。琉球の文化に魅せられた鎌倉は、首里城のフィールド調査も熱心に行っていた。そんな鎌倉が首里城取り壊しのニュースに触れたのは、解体工事が行われる3日前のこと。鎌倉は大慌てで、研究仲間であった建築家の伊東忠太に連絡。政府にも影響力を持つ伊東を通じて首里城の文化的価値を訴え、解体は辛うじて中止となる。中止が決定したのは工事の直前だったという。なお、鎌倉が描き残した図面は、戦後の再建で大いに役立つことになる。

大正時代に撮影された正殿(写真左)と南殿(中央)。これ以前に軍営として利用されたことから、御庭の入り口となる奉神門は撤去されている(那覇市歴史博物館提供)
大正14年(1925)には旧国宝に指定され、本格的な修復を受けた首里城に最大の悲劇が襲うのは太平洋戦争末期のことであった。沖縄守備軍が首里城の地下に司令部を設けたため、アメリカ軍の攻撃の対象となった。「鉄の暴風」と表現されたほどの容赦ない空爆や艦砲射撃により、首里城の建造物や城壁はいっさいが破壊されたのである。太平洋戦争では国内の多くの城郭建築が焼失したが、首里城は原爆投下のあった広島城と並び、“壊滅的”または“消滅”と表現できるほどの被害だった。

沖縄戦で破壊された首里城。アメリカ軍の砲撃により、ほぼ更地と化してしまった(沖縄県立平和記念資料館所蔵、那覇市歴史博物館提供)
沖縄の人々とともに歩み続ける首里城
戦後、沖縄はアメリカ軍の占領下に置かれた。日本本土の占領は昭和27年(1952)に終了するが、沖縄は昭和47年(1972)の日本復帰まで27年間も占領下にあったのである。
アメリカの施政下でも首里城復元の声は上がったというが、取り上げられることはなかった。戦後、首里城跡には琉球大学が建てられ、昭和54年(1979)に大学が移転するまで城として顧みられることは少なかった。今回の大火災後、那覇生まれの作家・池上永一さん(琉球王国を舞台にした小説『テンペスト』の著者)が新聞に寄稿したところによると、「(著者の幼少期は)『首里城』という名称ではなく『琉球大学跡地』と呼ばれるのが普通だった」という(「朝日新聞」2019年11月1日朝刊より)。

首里城のシンボルタワーの一つである守礼門。ほかの建物群に先駆けて昭和33年(1958)に復元。今回の大火災では焼失をまぬがれた
琉球大学移転が決定する前後から首里城再建が議論されはじめ、1980年代に入ると国と県による再建計画が策定された。しかし、復興事業は当初から難航を極める。沖縄戦によって建造物だけでなく、多くの歴史資料も灰燼に帰してしまったからだ。首里城というと華麗でどこかエスニックな雰囲気を漂わせる赤瓦が印象的だが、当時は屋根瓦が赤かったか黒かったかさえわからず、残された史料をしらみつぶしにあたり、古老にヒアリングして検証する日々が続いたという。
首里城復興プロジェクトは、単に城郭建築の復元にとどまらなかった。首里城は「建物自体が工芸品」と称されるように、琉球・沖縄の美の結晶体であり、建築や土木だけでなく、彫刻や瓦、漆工芸など多様なジャンルが結集し協力しなければ成し遂げられない事業であった。戦争により多くの職人や宮大工も亡くしていたが、時には本土の職人や研究者も参加し、力を合わせて再建は進んだ。
また、首里城は日本の城とも中国の城とも異なる独自の城郭建築であるため、復元には歴史学や考古学による調査と裏付けが必須であった。首里城復興を通して沖縄の歴史・考古研究は大いに進展し、「琉球沖縄史」が独立した学問分野として語られる一助にもなったという。
本土復帰20周年の記念事業として平成元年(1989)にスタートした再建工事は平成4年(1992)にひとまず完成し、首里城公園として開園。その後もプロジェクトは継続され、平成31年(2019)1月には国王と家族が居住した御内原(おんうちばら)のエリアが完成し公開されたばかりだった。平成12年(2000)には九州・沖縄サミットの舞台にもなり、かつて中国の使節をもてなした北殿が利用され、主要国首脳を歓迎する夕食会が開かれている。
4人に1人が亡くなるほどの沖縄戦や、長きにわたる米軍の占領という苦難を乗り越えてきた沖縄の人々にとって、首里城は琉球・沖縄のシンボルであり、その再建は悲願であった。かつて首里城復元の委員を務め、『琉球王国』『沖縄問題』などの編著もある高良倉吉さん(現・琉球大学名誉教授)は、首里城復興の意義を「人の命は取り戻せないけれども首里城を復元すれば、沖縄の魂は取り戻せると思った」と表現している(「毎日新聞」2019年11月1日朝刊より)。また、前述の池上さんは、「(復元された)首里城が私にもたらしたのは、ウチナーンチュの私を肯定してくれる意識革命だった」と記している(「朝日新聞」2019年11月1日朝刊より)。
首里城は、沖縄の人々のアイデンティティに寄り添う存在である。だからこそ、今回の大火災は沖縄の人々にとって痛恨の出来事であり、失われたものは大きい。復元にあたっては職人や資材の不足も指摘されているが、「それでも前回の再建に比べれば、資料も人材も条件もそろっている」という意見のほうが強い。首里城は五度よみがえり、また丘の上に華麗なる姿を見せることだろう。

国をあげての再建が決まり、県内外から多くの寄付金が集まっている。元の姿を取り戻すまで、できる限りの支援を続けていきたい
執筆・写真/かみゆ歴史編集部(滝沢弘康)
「歴史はエンタテインメント!」をモットーに、ポップな媒体から専門書まで編集制作を手がける歴史コンテンツメーカー。手がけるジャンルは日本史、世界史、美術史、宗教・神話、観光ガイドなど歴史全般。城関連の編集制作物に『図解でわかる 日本の名城』(ぴあ)、『廃城をゆく ベスト100城』(イカロス出版)など。
※近代以前の琉球史は日本史と異なるため、明治以前の出来事に関しては元号を使用せず西暦のみで説明しています