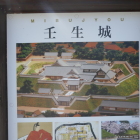壬生城は文明年間(1469~86)に壬生綱重によって築かれたとされています。戦国時代に100年もの間、壬生氏の城として存続しますが、豊臣秀吉の小田原攻めに際して壬生氏も滅んだとされます。江戸時代には日根野氏一万石、阿部氏二万五千石、三浦氏二万石、松平氏四万二千石、加藤氏二万五千石と次々と城主が変わりましたが、正徳2年(1712)鳥居忠秀が近江水口から移封してきてからは明治維新までの160年もの間、鳥居氏三万石(実質四万八千石)が代々の城主となりました。
かつては本丸の周囲を二の丸、三の丸が囲み、東郭、下台郭、正念寺郭の六つの郭で成り、各郭は土塁と堀で囲われていたようです。また東郭の先の大手門は丸馬出しのようになっていたようです。現在は本丸周辺が壬生城址公園として整備されていて、鳥居氏が転封してきた際に建てられた精忠神社は鳥居元忠公を祭神として祀っています。
+ 続きを読む