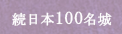牧志からバスで座喜味下車。
バス停付近には座喜味城の気配はありません。
一体どんなふうに現れるんだろう?とわくわくしながら住宅街を歩きました。
徒歩約15分で到着。
この日は一日雨予報でユンタンザミュージアムも閉館日でした。長の道中、こんな日もあります。気にしません。
結界のような木立の道を抜けた先に、霧のベールに包まれた城壁が現れました。一体どれくらいの大きさなのか、ここからでは確認できません。しかし大きくカーブを描く石の壁は謎めいて神秘的。自然と気持ちも引き締まります。
アーチ門を潜ると幻想的な空間が広がっていました。独り占めするのが申し訳ないくらいです。
同時に戦中戦後の使われ方にも首肯する閉塞感があり、時代の変遷と共に生きてきた城であったことを思いました。
帰る頃にはぼちぼちと来訪者もいらっしゃり、「晴れていなくて残念だったね。」と声をかけられましたが、(今日のこの景色が見られて幸せでした。)と心の中で返事をしました。
+ 続きを読む