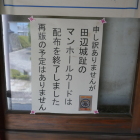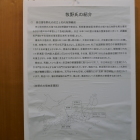田辺城の櫓門は田辺城資料館、隅櫓は彰古館として公開されています。内容は細川藤孝にまつわる物が多く、文武両道を極めた古今伝授の継承者であり優れた文化人であることが伺えます。息子の忠興は気が短いことで知られ残虐なエピソードも多く残りますが、千利休に師事し利休七哲の一人に数えられています。また武家茶道の一つ、三斎流の祖とされ門人も多くいたようです。家康の影響か薬学にも通じていたとされ、徳川秀忠の奇病が万病円で回復した時に寄生虫(寸白)が原因であると見ぬいています。とはいえ万病円にはヒ素や水銀が含まれていて荒療治どころか寿命が縮みかねないわけですが。
+ 続きを読む