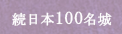この日最後の登城は帰り道の引田城、再訪です。
引田港側の登城口から登っていきます。
小雪がちらつく時間帯もあり寒かったのですが登れば温まります😌
本丸の石垣を見上げ天守台へと進みます。
ここからは引田港を見下ろします。
本丸は城下からもよく見え、権力を示すことができる位置にあります。
ここから下る道があり化粧池、ここの石垣は他の石垣より後に築かれたものです。
ここから登り、灯台を経て東の丸へ。
ここからの眺望も素敵、女郎島を望みます。
東の丸にも石垣が残っています。
さらに北二の丸、お馴染みの二段になった石垣があります。
上段にはまだビニールシートが掛けられていて一部しか見ることは出来ません。
北曲輪まで行って引き返しこの日の目的である大手道から下りていきます。
大手道は一部推定とのことですが下の方に家臣団屋敷の推定地があります。
土塁が築かれ広く削平されています。
ここから下ると民家の脇に出てきました。
尚、ここからの案内板はありません😔
【見どころ】
・本丸の石垣
・天守台からの眺望
・化粧池の石垣
・北二の丸の石垣
・家臣団屋敷
+ 続きを読む