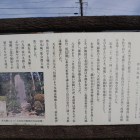【大河内城】
<駐車場他>松坂市大河内城地区市民センター前駐車場または搦手門前に住民の方が駐車場として5台分程の広場を開放してくださっています。市民センターの扉前に地図・縄張り図のコピー、御城印が入ったクリアファイルがあり、もらえます。ありがたく頂戴。
<交通手段>車
<見所>堀切
<感想>日帰り伊勢山城攻め旅ラスト7城目。現地説明板によると大河内城は1415年に北畠満雅が阿坂城で室町幕府に反旗を翻したとき、築城して弟の顕雅を籠城させたとあります。以降顕雅は大河内氏と名乗り北畠氏の諸流となり北畠氏を支えます。大河内城の戦いで織田信長軍が攻めてきた時には北畠具教は多気の霧山城から大河内城に本拠地を移して籠城戦をします。織田軍は落城させることができず和睦し織田信雄を養子に入れます。
市民センターから歩くと阪内川が南北に流れていて天然の要害さが良く伝わってきます。北の大手口から登って南の搦手口へ出ました。当時は丘陵地全体が城だったようですが現在は主要部が神社として整備されています。主要部は主郭の東側が二の丸と広い馬場があり、北側は谷に、西側は堀切があり西の丸があります。西の丸は帯曲輪で取り巻いています。主要部は期待より小さい感じを受け、安濃城跡より小規模な感じを受けました。これにてこの旅終了、本格的山城の阿坂城はもっと冬枯れになったら行くつもり。走行距離296㎞無事走破。
<満足度>◆◆◇
+ 続きを読む